BOOKS

–1984–
BEDTIME STORIES
OSAMU GOODSマザーグースのキャラクターが、9編の楽しい物語の主人公になった短編小説。
秋山道男さん、鈴木海花さん、林真理子さん、酒井チエさん、
安西水丸さん、秋山猛さん、佐々木克彦さんら豪華な作家陣が参加。
夢の中でも幸せな気分になれる本として、ファンなら誰もが枕元に置いていた本。
原田治さんの素敵な挿絵を掲載。
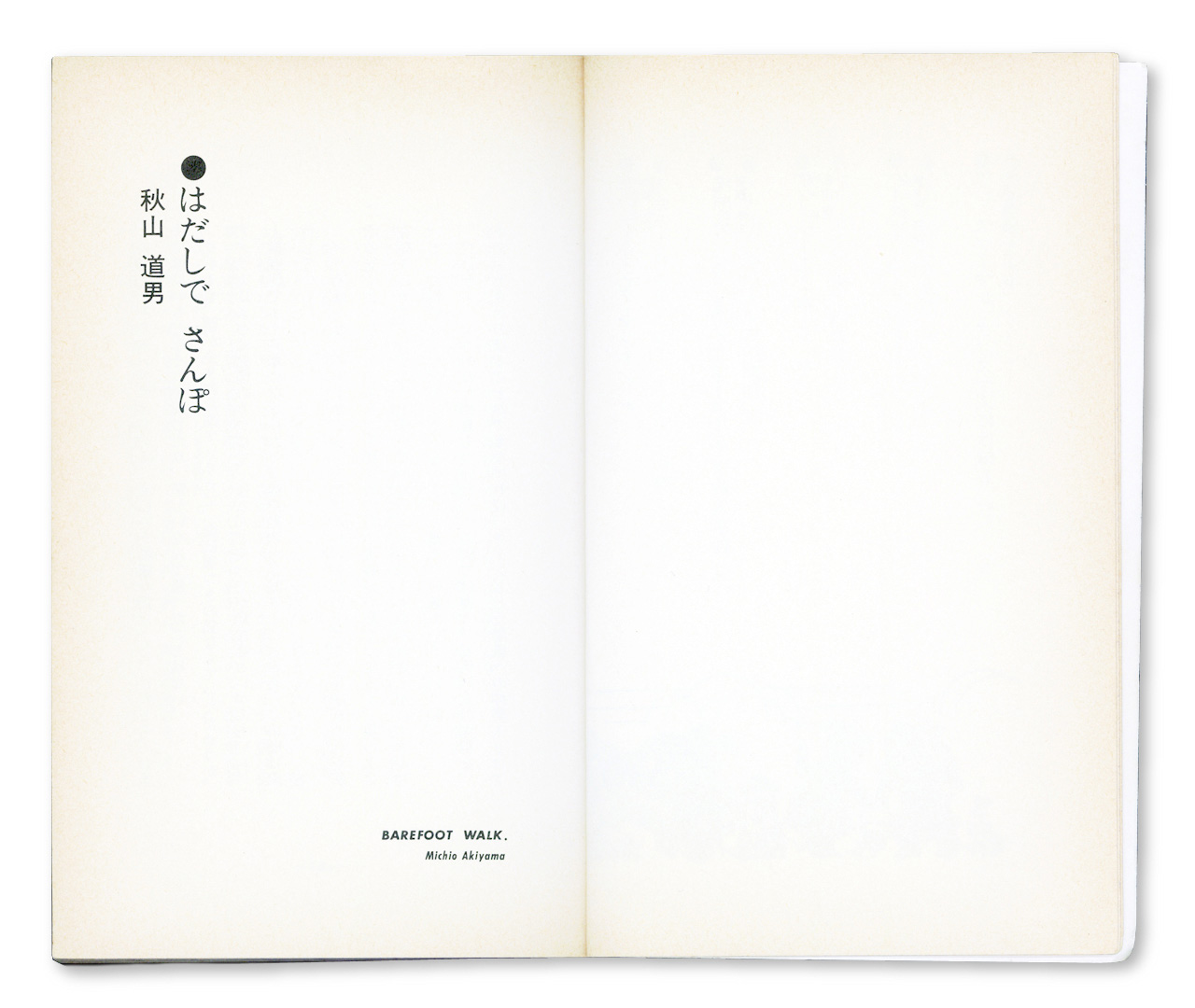
はだしでさんぽ/秋山 道男
ブッチ・スプリングティーンは、俗にいう雑種の猫だった。だけれども、いままで彼はいちどもそれを恥じたり、悲しいなんて思ったことはない。
そもそも、彼が生まれた国アメリカに、血統書つきの猫なんていただろうか。アメリカはまさに猫種のるつぼで、ほとんどすべてが混血猫といってもいい。
上猫議院でよく問題になるけれど、他の動物と結婚することさえ、この頃は流行している。
ブッチは一度、ニューオルリンズで、かわいらしいネズミの花嫁をつれた新婚の猫に会ったことがある。花婿は他の猫の視線が心配でたまらず、頭の上に花嫁をのせて、しずしずと歩いていた。ニューヨークなんかさすがにすすんでいて、父親がライオンという、ものすごく雄々しい猫もいるという話だ。
だけど——ブッチはため息をついた。この国では違う。五代以上の先祖を、キチンとさかのぼることができなければ、キチンとした階級への仲間入りはできないのだ。ミルフィユのそばにだっていくことはできやしない。
ミルフィユ——なんて美しい名前なんだろう。彼の国アメリカの西部あたりで、フィドゥルと呼ばれるバイオリンが、このフランスではヴィオロンという、流れるような名前がつくように、彼女の美しさのすべてその名前にあらわされていた。
彼女の先祖は、なんと二十代以上にさかのぼることができるという。その昔、マリー・アントワネットの愛猫として、ペルシャ王室から献上されたのが、彼女の祖先だったそうだ。ベルサイユ宮庭の奥深く、その真白なペルシャ猫は非常に珍重され、上質の香油数種とマタタビを混ぜ合わせたもので、毎日毛並みをよくするためにマッサージをうけたという。
ミルフィユは、その雪のように白くて毛足の長い肌と、気品の高さを、そっくり遺伝でうけついだ、由緒正しいペルシャ猫だった。
ブッチが入学した、パリ郊外のアルジャントイユ村にある、マルメイユ音楽院ピアノ科の、彼女は優等生だった。
彼女と初めて会った日の、胸が文字どおり震えた春の午後を、ブッチは今だにはっきりとおぼえている。
マルメイユ音楽院の庭は、白いバラが盛りだった。
ふと流れるショパンのワルツが気になって、ブッチは、あずま屋風の練習室をのぞいた。
そこに彼は白バラの精のような、真白い猫を見たのだった。
漆黒のグランドピアノに、彼女のノーブルな横顔が映えて、息をのむような美しさだった。
アメリカで、こんなまざり気なしの真白い猫など見たことはない。
彼女は視線を感じてふと目を上げた。その目の青く澄きとおっていること!
ブッチはやっとのことで、習いたてフランス語で非礼をわびた。
「パルドン、マドモワゼル、練習中失礼いたしました。」
「かまいませんわ……あなたアメリカの方?」
「え、ええ。今度バイオリン科に入学したブッチ・スプリングティーンといいます。あ、あなたの名は?」
「ミルフィユ・エトワール・フランシーヌ・ドゥ・リュクサンブールと申しますの。正式にはもっと続くんですけれども……」
彼女のフランス語は実にすばらしかった。それもそのはず、彼女は生粋のパリニャンヌだったのだ。
それからの半年、ブッチはミルフィユのために生きてきたといってもいい。
夜、下宿屋のベッドで寝る時も、ルナール教授の前でバイオリンをかかえている時も、あのミルフィユの青い瞳を、彼は忘れることができなかった。
彼女に会うために、ぼくはこのヨーロッパにきたのだ。僕が本やレコードで憧れつづけてきたヨーロッパ、何日も続く船旅の最中、暗い貨物船の底で、ずうっと思いつづけてきたヨーロッパ、ああ、ミルフィユこそ、この大陸そのものなんだ。
