BOOKS

–1984–
BEDTIME STORIES
OSAMU GOODSマザーグースのキャラクターが、9編の楽しい物語の主人公になった短編小説。
秋山道男さん、鈴木海花さん、林真理子さん、酒井チエさん、
安西水丸さん、秋山猛さん、佐々木克彦さんら豪華な作家陣が参加。
夢の中でも幸せな気分になれる本として、ファンなら誰もが枕元に置いていた本。
原田治さんの素敵な挿絵を掲載。
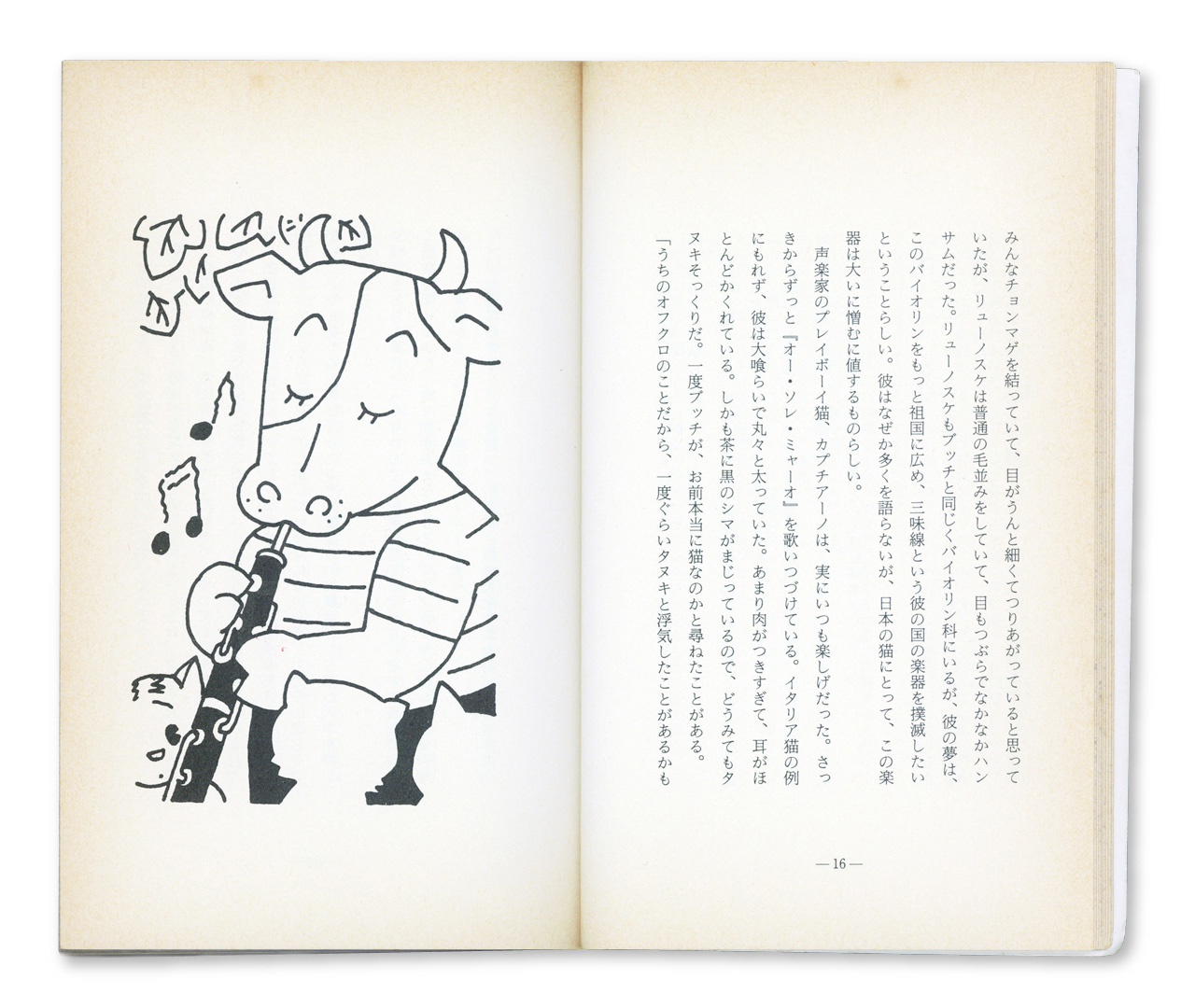
はだしでさんぽ/秋山 道男
初秋のさわやかな午後、ブッチはクラスメイトたちと、近くの森へピクニックに出かけた。セーヌ河の魚のフライと、ボルドー酒の一びんが一行をいっそう陽気にしていた。
日本から来た留学生の、三毛猫のリューノスケ。ブッチは日本猫というのは、みんなチョンマゲを結っていて、目がうんと細くてつりあがっていると思っていたが、リューノスケは普通の毛並みをしていて、目もつぶらでなかなかハンサムだった。リューノスケもブッチと同じくバイオリン科にいるが、彼の夢は、このバイオリンをもっと祖国に広め、三味線という彼の国の楽器を撲滅したいということらしい。彼はなぜか多くを語らないが、日本の猫にとって、この楽器は大いに憎むに値するものらしい。
声楽家のプレイボーイ猫、カプチーノは、実にいつも楽しげだった。さっきからずっと『オー・ソレ・ミャーオ』を歌いつづけている。イタリア猫の例にもれず、彼は大喰らいで丸々と太っていた。あまり肉がつきすぎて、耳がほとんどかくれている。しかも茶に黒のシマがまじっているので、どうみてもタヌキそっくりだ。一度ブッチが、お前本当に猫なのかと尋ねたことがある。
「うちのオフクロのことだから、一度くらいタヌキと浮気したことがあるかもしれないね。」といって、彼は片目をつぶった。
さて、もうひとりの仲間がきている。その仲間というのは、ブッチたち三人のおしりの下にいた。皆を背に乗せて、のっそりと歩いている牛のペペだった。
牛が入学してきたのは、伝統あるマルメイユ音楽院でも前代未聞のことだった。教室も机も彼が使うにはケタはずれに小さいので、校長はじめ何人かの教師があきらめるように説いたのだが、ぺぺはなにもいわず、ただその悲しそうな目でジッと見つめるだけだったので、皆はついに根負けして彼の入学を許したのである。
彼はもちろん教室に入らないので、校庭にじっとすわり、窓から首だけ出して講義を聞いていた。時々顔が見えなくなるので、ブッチが心配して窓からのぞくと、お腹が空いたらしく庭のクローバーを食べていた。
ペペは器楽科でオーボエを習っていたが、教授に叱られた時、思わず本来の声で叫んだことがある。その声が、彼がいままで出したどのオーボエより美しかったとほめられ、ペペは大いにくさっていたものだ。
森は黄金に輝いていた。大部分がイチョウの木で、落ち葉がすばらしい自然のカーペットとなって、四人がころげまわって遊ぶのを心地よいものにしてくれた。
ふとブッチは、サッと影が横切ったのを感じで身を起こした。イチョウの木の中に見えかくれする白い姿。なんとあのミルフィユが目の前にいた!
あまりにも突然のことと、今までの自分の子どもっぽい行為を見られた恥ずかしさに、ブッチはサッと赤くなった。
ミルフィユはほほえみながら近づいてきた。ゆっくりと落ちていくイチョウの葉を背景に、白い巻き毛がこのうえなく美しい。
「ひ、ひさしぶり、お元気でいらっしゃ、しゃいましたか。」
「ええ、ありがとう。」
その時、ブッチは世にも不思議なふたりを見たのだった。白くのっぺりした丸顔の女と、頭がヘンに丸いピッカピカのやせた男。彼らはあるでミルフィユを護るように、ぴったりと後ろにくっついていた。
「ご紹介するわ、親友のサラとサージー氏よ。」
「はじめまして。」
ピッカピカの方が、腰をかがめて馬鹿ていねいなあさいつをしたので、ブッチもあわてて頭をさげた。
「私たち、あちらの湖の方へ行っておりますので、ではまた。」
背を向けたミルフィユに、あわててブッチは声をかけた。今このチャンスを逃せば、校庭の片隅で、そっと彼女の姿をかいま見る毎日が続くだけなのだ。
「あ、あのミルフィユ嬢、あとでお話をしにお伺いしてもいいでしょうか。」
ミルフィユはちょっと驚いたようだったが、静かにうなずいた。彼女が立ち去ると、カプチーノが興奮して声をかけてきた。
「スゴイじゃない。ピアノ科のマドンナ、わがミルフィユ嬢にアタックするなんてさ。」
「でもちょっとお高いねえ、ワタシの国じゃ女はあんなにえばらせないもんだけどねぇ。」
「僕は真剣なんだ!」
ブッチは自分でも驚くぐらい大きな声を出した、ああ、どうやったら分かってもらえるんだろう。ミルフィユを思ってシーツをかじった夜、思い出の白バラを見ると、たまらずに食べてしまう癖がついたこと……。
「黙ってておやり。恋をしているものをからかうなんて、いちばんいけないことだよ。」
ペペがいつものように静かな声でいった。
「ペペは誰かを好きになったことがあるのかい。」
ぺぺは黙ってうなずいた。ブッチは静かな彼の目をみると、いつも満たされたやさしい気持ちになるのだ。種族やからだの大きさを超えて、ペペとは本当にしみじみとした気持ちが通じあえる、とブッチは思う。
ぺぺが恋した相手とは誰なんだろう。クローバーが大好きなめ牛かしらん―。
ブッチは考えると楽しかった。
