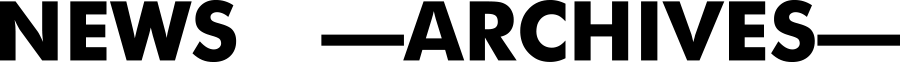『少女時代によろしく』、『水森亜土』、『女學生手帖』など、著書多数な、弥生美術館学芸員内田静枝さん。今回の『オサムグッズの原田治展』の企画を行い、展示商品のセレクトや設営、期間中の様々な取材受付も担当されました。オサムグッズを集めた少女時代の経験談と、大正期から連なるイラストレーターのグッズの歴史を俯瞰されたギャラリートークは来場者の皆さんにとっても興味深いお話だったのではないでしょうか。弥生美術館の一階に展示されたオサムグッズを眺めながらの説明はとても分かりやすく、改めてその魅力を掘り起こす50分間となりました。前編に引き続き、中編をお届けします。
原田先生がご自身でもオフィシャルサイトなどにお書きになっているのですけれども、キャラクター作りのときに、これまでの日本のキャラクターを調べてみると「女の子が泣いている」又は「泣いているキャラクター」というのはなかったそうです【1】。それなら泣いてるキャラクターを入れてみようという風に、新しいチャレンジをされたそうです。
意外にこの泣いている女の子を憶えているファンの方は多いようで、展覧会のミュージアムグッズコーナーで、「この泣いている女の子のスクールバックはないですか?」というようなことをお尋ねいただきます。すごくインパクトがあったんじゃないかなと思います。
そして、赤ちゃんのキャラクター【2】、これもオサムグッズが出るまではなかったそうです。

オサムグッズが発案の下敷きにした『マザーグース』は、明治時代に日本に入り、翻訳などが行われました。イギリスの古い民謡・古謡ですね。これをキャラクターの世界に持ち込んだのが原田治さんです。そして、明治時代にいち早くマザーグースを取り入れていた画家がいます。お分かりになりますでしょうか?
竹久夢二です。夢二は自分なりにマザーグースを解釈し、絵を描いています。原田治さんとニュアンスは異なりますが、こちらの女の子の絵は夢二版"ジル"【3】、といった所でしょうか。猫もありまして、これが夢二版"キャット"【4】でしょうか。原田先生の"ジルとキャット"【5】を見比べて頂いても面白いかなと思います。

さて、初期のオサムグッズのキャラクターと、中期以降のオサムグッズのキャラクターの違い、お分かりになりますか?どなたかお分かりになる方いらっしゃいますか?(ギャラリートーク参加者の方が「目」と答える)そうです、目ですね。目の描き方が少し違っています。初期のオサムグッズは目が真ん丸で切れ込みが入っているんですね。これはスライスドアイと呼びます。パイをスライスしたような形ですね、アメリカのアニメーションの最も古い技法だそうです。これを原田治さんはキャラクター作りに取り入れました。ただこの描き方だと幼い子どもの表情しか描けないということがありまして、やがて縦長の楕円形の目になっていったそうです。その目を描くにあたって参考にしたのは、アメリカのカトゥーンの『原始家族フリントストーン』のキャラクター、美人妻のウィルマです。原田治さんはウィルマの大ファンでその影響で、やがてオサムグッズのキャラクターたちは、彼女のような目になっていったそうです。

左側のレコードバックに描かれたキャラクターが初期のもの。目がパイをスライスしたような形のスライスドアイになっている。右側グッズは中期以降。
オサムグッズのキャラクターグッズは、実際に数えたわけではありませんが、おそらく1000点以上あると思います。今回の展覧会では、『トムズボックス』という絵本編集プロダクションの土井章史さんが集められたものを、特別に公開させていただくことになりました。
では、原田治さんのこれまでの道のりについてお話いたします。
原田治さんは1946年、東京の築地に生まれました。幼い頃から絵を描くことが得意で、抽象画家の川端実のアトリエに通っていました。川端実は日本を代表する抽象画家で、アメリカでも活躍された方です。そして原田治さんは青山学院の中学・高校を経て、多摩美術大学のグラフィックデザイン科に入学しました。東京生まれ・青学ボーイ・多摩美の多摩グラ、という王道をゆくシティボーイだったと私は思うのですけれども、大学時代は学生運動が盛んで、余り大学では勉強しなかった、遊んでばかりいた、というようなことを言っておられます。
その頃、アメリカンファーマシーというお店が日比谷にありまして、そこに入り浸っていたそうです。(ギャラリートーク参加者に向かって)アメリカンファーマシーってご存知でしょうか?ファーマシーですから、つまり「薬局」ですが、そこは在日アメリカ人向けの薬局であり、日本とアメリカの薬局のあり方というのはちょっと違うようで、薬だけでなく生活雑貨や文房具なども売っていました。そして一角にはソーダーを提供するようなソーダーファウンテンを持っているお店などもあったそうです。原田治さんはアメリカ産の素敵な雑貨がたくさん集まる店で、デザインの素晴らしさを学んだようです。
そして、実家が築地にある輸入食品を扱う店であったため、アメリカからの輸入食品や缶詰が山のように積まれていまして、あのキャンベルスープ缶などですね。そういうものに親しんで育ったそうです。また幼い頃からの映画マニアであったそうです。原田治さんのブログ『原田治ノート』を読むと、相当な映画好きであることがよく分かりますね。たくさん映画を観ていらっしゃいます。そして原田治さんの祖父は、二川文太郎という映画監督さんでいらっしゃいました。『雄呂血』という日本の古い映画の名作を監督をされた方です。
1969年に原田治さんは大学を卒業し、アメリカに渡ります。原田治さんの誕生は終戦の翌年で、終戦直後に生まれた日本人は、大なり小なりアメリカ文化の影響を受けています。原田治さんは特にその憧れが、心に強く擦り込まれていたのではないでしょうか。渡米された1970年当時のアメリカというのは、ベトナム戦争の影が色濃く残っており、それが社会全般に影響していて、フラワームーヴメントが広がりヒッピーなどが出てきたりで、原田治さんが憧れたかつてのアメリカ文化というのはもう既に無くなってしまっていた、ということだったそうです。自分の憧れたアメリカはもう既に何処にも無いという、ノスタルジックな気持ちが原田先生の中に強く残ったそうです。
そして、アメリカ遊学を1年で切り上げ、日本に1970年に帰国します。この1970年というのは日本の雑誌界において、エポックメイキングな年です。何故かと言いますと、雑誌『an an』が創刊した年なんですね。『an an』というのは今もありますが、大判の総グラビア印刷の雑誌であり、これは日本の出版界では画期的なことでした。当時は"アンノン族"っていう風に言われたりで、その元になったのが雑誌『an an』であり、追随した雑誌『non-no』でした。そういった雑誌には"旅特集"が掲載され、若いOLが『an an』や『non-no』の旅特集を参考にして、全国各地に出掛けていった、そんな時代だったのです。私はその時は幼い子どもだったので実感は出来ていませんが、『an an』や『non-no』を小脇に抱え、軽井沢に行ったり清里へ行ったりするのが、若い女性の一番トレンドだったんじゃないか、と思います。